看護師国家試験の必修問題で、毎年のように出題されている鉄板テーマが「介護保険制度」です。
制度の仕組みを覚えておくだけで、確実に得点できる“落としてはいけない得点源”です。
この記事では、介護保険制度の概要をわかりやすく整理しつつ、国試で問われやすいポイントを5つに絞って解説します。
必修対策の総仕上げとして活用してください
✅ 出題傾向の全体像
- 毎年必ず出題されるテーマが存在する
- 落とすと合否に直結するほど重要
- 確実に得点できれば合格に大きく近づく
今回は、介護保険制度の必修問題の出題傾向をもとに、頻出テーマをまとめました。
毎日ちょっとずつ、「1問だけでもやった」と積み重ねていくことが大切です。
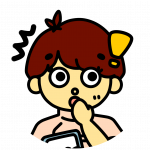 なすこ
なすこ必修科目のボーナス問題!だったの・・・



頻出ポイントはあります❗️
では、具体的に説明していきますね‼️
模試結果を分析して、あなただけの国試対策アドバイスを!無料相談限定受付中
📲 学習をサポート!公式LINEでセミナー情報や役立つテクニックを配信中!
\ 無料でお友達登録!/
🙋 模試や過去問演習で必修の正答率が8割に届かず不安を抱えている人
🙋 既卒・再受験組で暗記分野を落としがちな人
🙋 暗記より理解派で統計や制度を後回しにしている人
看護師国試対策は、効率的な学習法で結果を出すことが大切です。試す価値、大アリです!!
介護保険制度が必修で出題される理由
「健康支援と社会保障制度」分野は、看護師国家試験の必修で毎年2〜3問ほど出題されます。
その中でも介護保険制度は特に出題頻度が高く、過去10年で複数回出題されています。
なぜこれほど出題されるのか?
それは介護保険制度が、日本の高齢化社会を支える根幹制度だからです。
制度の仕組みや対象者、自己負担割合を正確に理解することは、臨床現場でも欠かせない知識となります
介護保険制度の概要:5つの必修ポイント
① 対象者(被保険者)
- 第1号被保険者:65歳以上のすべての人
- 第2号被保険者:40〜64歳の医療保険加入者
👉 「第2号=65歳以上」と誤解しやすいので要注意!
実際の出題(例) 第106回必修
「介護保険の被保険者について正しいのはどれか」
→ 正解:65歳以上の者は全員加入する
②保険者(運営主体)
保険者は 市町村・特別区
👉 「都道府県が運営」と混同してしまう受験生が多いので、確実に覚えましょう。
👉 混同しやすいポイント:「介護=市町村」「後期高齢者医療=都道府県広域連合」と整理すると理解しやすいです。
介護保険→市町村・特別区
国民健康保険 → 都道府県・市町村・国民健康保険組合(ただし財政運営は都道府県)
後期高齢者→ 後期高齢者医療広域連合(都道府県単位で全市町村が加入する)
看護師国試対策では、同じ様なものは比較して対比して覚えておくのがコツです!!
③財源(お金の仕組み)
- 財源は 公費50%+保険料50%
- 公費の内訳:国25%、都道府県12.5%、市町村12.5%
- 保険料は、第1号被保険者(65歳以上)と第2号被保険者(40〜64歳、医療保険加入者)が負担します。
👉 「公費50%+保険料50%」を大枠で覚え、内訳も補足できると得点に強いです。
④サービス内容
- 在宅系:訪問介護、訪問看護、デイサービス
- 施設系:特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)、介護老人保健施設、介護医療院
- 地域密着型サービス:グループホーム、小規模多機能型居宅介護
👉 試験では「どのサービスが介護保険に含まれるか?」が問われやすいです。
⑤利用者負担(自己負担割合)
- 原則:1割負担
- 一定以上の所得がある場合:2割または3割負担
👉 「すべて1割」と思い込むのは危険!国試ではここをよくひっかけてきます。
試験で狙われるひっかけパターン
- 保険者=都道府県(✕) → 市町村が正解
- 第2号被保険者=65歳以上(✕) → 40〜64歳の医療保険加入者
- 利用者負担=一律1割(✕) → 所得に応じて変動
- 要介護認定=市町村長が判定(✕) → 介護認定審査会が判定
- 介護保険サービス=すべて施設系(✕) → 在宅・地域密着型も含む
👉 このような誤答を防ぐために、制度の流れをしっかり整理しておくことが大切です。
一問一答で復習
Q1. 介護保険の第1号被保険者は?
A. 65歳以上のすべての人
Q2. 介護保険の第2号被保険者は?
A. 40歳以上65歳未満の医療保険加入者
Q3. 介護保険の保険者は?
A. 市町村および特別区
Q4. 介護保険の財源は?
A. 公費50%(国25%、都道府県12.5%、市町村12.5%)+保険料50%
Q5. 介護保険の「施設サービス」に含まれるのは?
A. 特養、老健、介護医療院
Q6. 要介護認定の流れは?
A. 申請 → 一次判定(コンピュータ) → 二次判定(介護認定審査会)
Q7. ケアプランを作成する専門職は?
A. 介護支援専門員(ケアマネジャー)
過去問ピックアップ
過去問①:第108回 午前(必修)
設問:介護保険の第1号被保険者で正しいのはどれか。
→ 正解:介護保険被保険者証が交付される
(65歳の誕生日を迎える月に自動交付されます)
過去問②:第111回午前(必修)
設問:介護保険制度における「施設サービス」はどれか。
→ 正解:介護医療院サービス
(介護医療院は長期療養型の入所施設であり、施設サービスに分類されます)
国民衛生の動向でみる看護師国家試験の介護保険制度問題まとめ
1)一般財団法人 厚生労働統計協会
国民衛生の動向でみる看護師国家試験の介護保険制度問題まとめ
2)厚生労働省HP
介護保険制度について



この2つのHPは、受験生必読ですよ
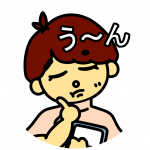
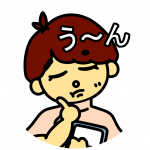
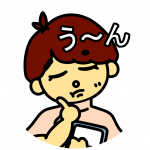
許可とかもこんがらがりますよね・・・
● 都道府県知事が権限を持つもの
- 居宅サービス事業者(例:訪問介護、通所介護など)
- 介護予防サービス事業者
- 介護保険施設
- 介護老人福祉施設(特養)=「指定」
- 介護老人保健施設(老健)=「許可」
- 介護医療院 =「許可」
※老健と介護医療院は、設置にあたって「許可」が必要。
※特に 老健・介護医療院は“許可”制という点が差別化ポイントです。



「広域性・専門性が高い施設やサービス」ほど、
都道府県知事の権限になる
● 市町村長が権限を持つもの
- 地域密着型サービス事業者
- 地域密着型介護予防サービス事業者
- 居宅介護支援事業者(ケアマネジャー事務所)
- 介護予防支援事業者(地域包括支援センターなど)



キーワードは 「地域」=住民に一番近い自治体=市町村長
補足(試験に出やすいポイント)
- 「介護保険施設」は 都道府県知事の指定・許可。
- 「地域密着型サービス」は 原則=市町村長の指定。
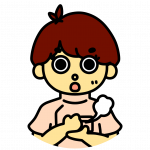
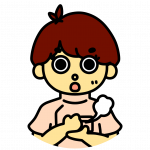
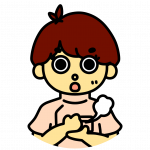
なるほど!全部を覚えるのではなく、まずは試験に出題されているポイントで絞れば良いんですね
まとめ:介護保険制度は必修の得点源
「看護師国家試験」の必修では、毎年のように介護保険制度の概要が出題されています。
出題されるのは制度の根幹部分であり、暗記すれば確実に得点できます。
- 対象者(第1号・第2号)
- 保険者=市町村
- 財源=公費50%(国25%・都道府県12.5%・市町村12.5%)+保険料50%
- サービス内容(在宅・施設・地域密着型)
- 利用者負担=原則1割(所得により2割・3割)
- 要介護認定の流れ
- ケアマネジャーの役割
👉 まずはこの部分を確実に押さえて肉付けをしていけば、必修対策として万全です。
「健康支援と社会保障制度」分野を攻略して、必修での取りこぼしゼロを目指しましょう!



次回は
保健師助産師看護師法で、絶対に押さえておく項目をピックアップしてみますね
何から始めればいいかわからない…
スケジュールをうまく立てられない…
解剖生理が苦手…
そんな悩みを持つ方のために、私たちは看護師国家試験に特化した個別学習サポートを提供しています。
現役看護師による分かりやすい講義、苦手分野の徹底フォロー、あなただけのスケジュール作成など、合格に必要なすべてを一緒に整えていきます。
今が、115回の試験に向けて、最高のスタート地点です。
もう少し時間があったら…
試験前の時期に嘆く前に、一緒に、「今年こそ絶対合格」をつかみ取りましょう!



暗記が苦手ではなく、「覚えるべきマト」と
「繰り返しの回数が足りないだけ」 です
心配な方は、遠慮なく無料相談で相談してくださいね
無料相談で何ができるの?
「勉強しているのに成績が伸びない…」
「どこから手をつけたらいいのかわからない…」
「既卒でどのように学習したら良いのかがわからない…」
そんな悩みを抱えていませんか?
なすゼミでは、看護師国家試験対策に特化した無料個別相談(30分)を実施中! 📝
無料相談で何ができるの?
✅ 模試の結果を徹底分析
✅ 今の勉強方法を見直し
✅ あなたに最適な勉強プランを提案
経験豊富なプロのサポーターが、あなたの悩みにしっかり耳を傾け、合格までの道筋を一緒に描きます。
📅 相談の流れは簡単3ステップ!
1️⃣ なすゼミ公式LINEを友だち追加
2️⃣ 専用予約フォームから希望日時を選択
3️⃣ オンライン相談で個別アドバイスをGET
👉 今すぐ公式LINEに登録して予約する
🎁 30分無料相談は期間限定! この機会に、あなたに合った合格戦略を手に入れませんか?
「合格」の二文字に近づくための第一歩、 今すぐ無料相談を予約しましょう!
👉 公式LINEに登録して無料相談を予約 あなたの夢を、なすゼミが全力でサポートします🌟
一緒に合格を掴み取りましょう!
\ 無料でお友達登録!/
看護師国家試験は人生の重要なステップですが、効率的な勉強法を取り入れることで、自信を持って挑戦できるはずです。
今回ご紹介した時間がない人のための勉強法方法は、試験だけでなく日常生活や将来の実務にも役立つスキルです。
合格ライン周辺の受験生に対する具体的な解決方法や勉強のコツをサポートしていますので、
気になる方は、ぜひ無料お試しで、遠慮なくご相談ください!


\ 今なら1ヶ月間無料お試し!/
こちらの記事もオススメです!
【「覚えられない」を解消!科学的に効率アップする記憶法】
https://nursta.jp/blog/nursta-jp-blog-strategy/
【なんで点数がこんなに伸びたの!?勉強の秘密を限定公開します!】
https://nursta.jp/blog/nursta-jp-blog-monina_recruitment2024/



学習方法での質問をまとめてありますので、ぜひこちらの記事を参考にしてくださいね。
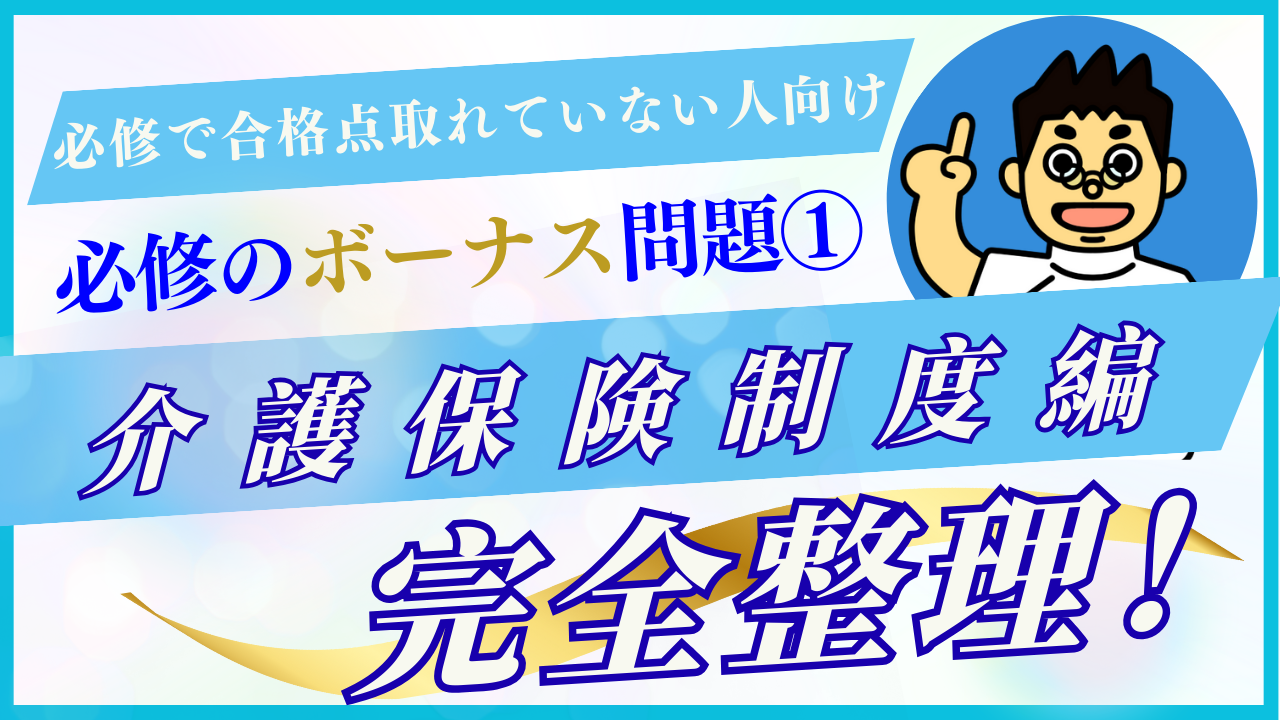

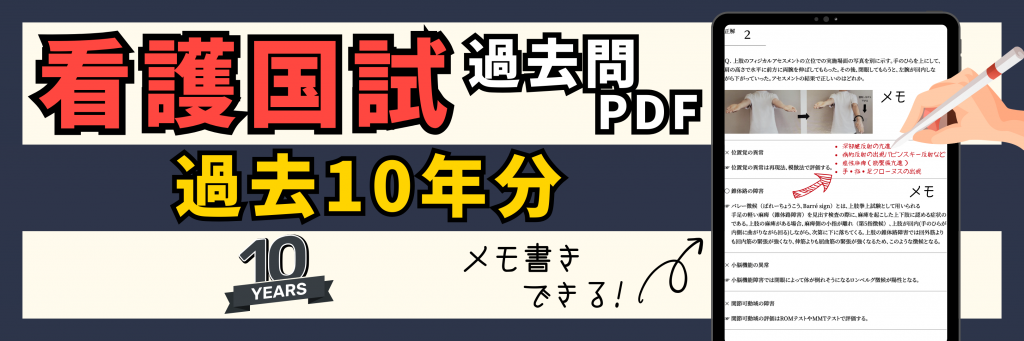

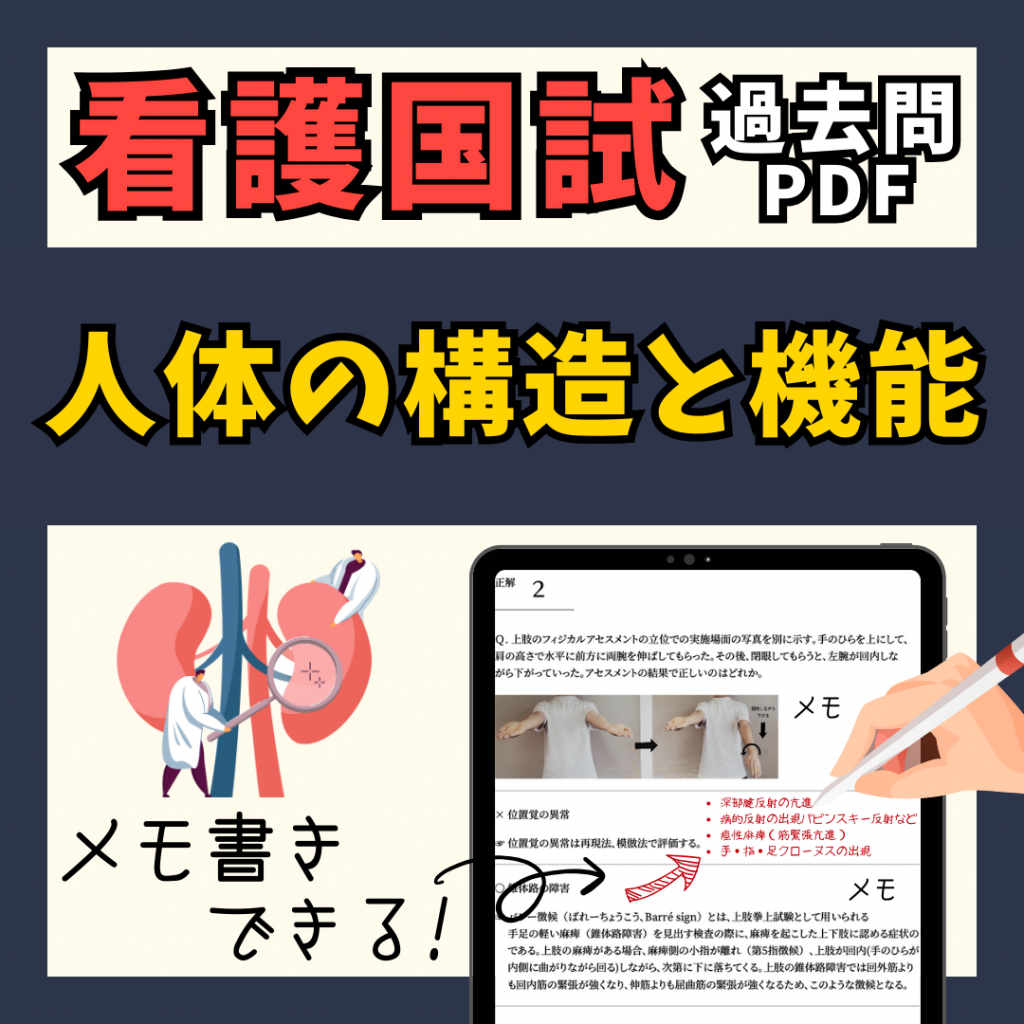
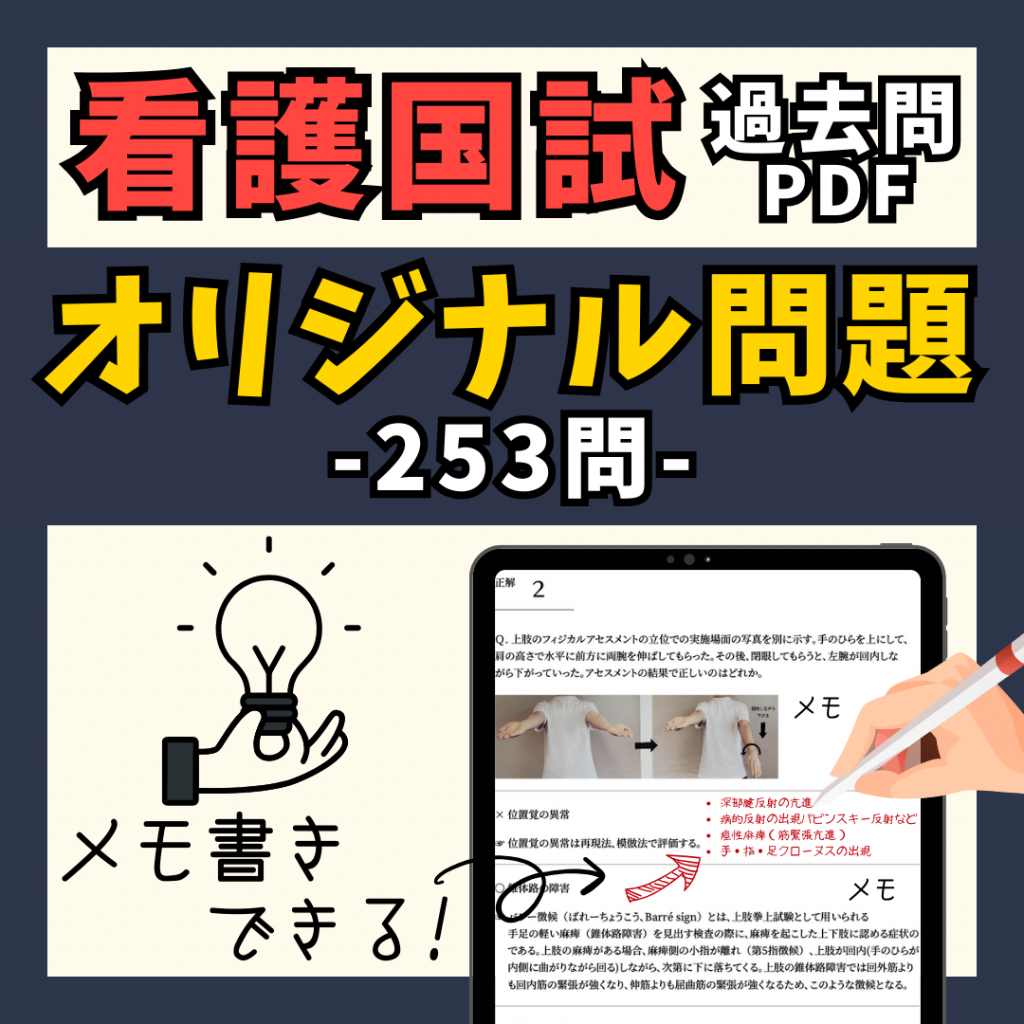
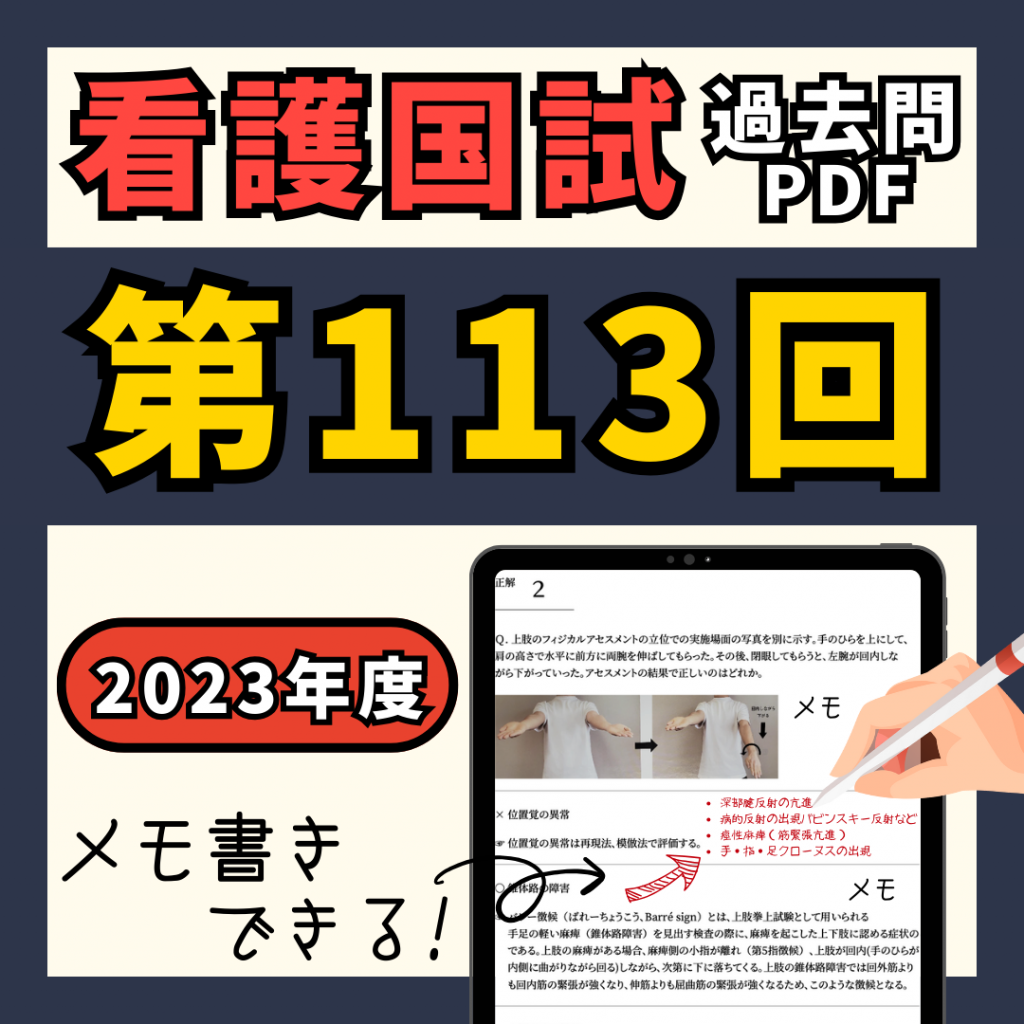
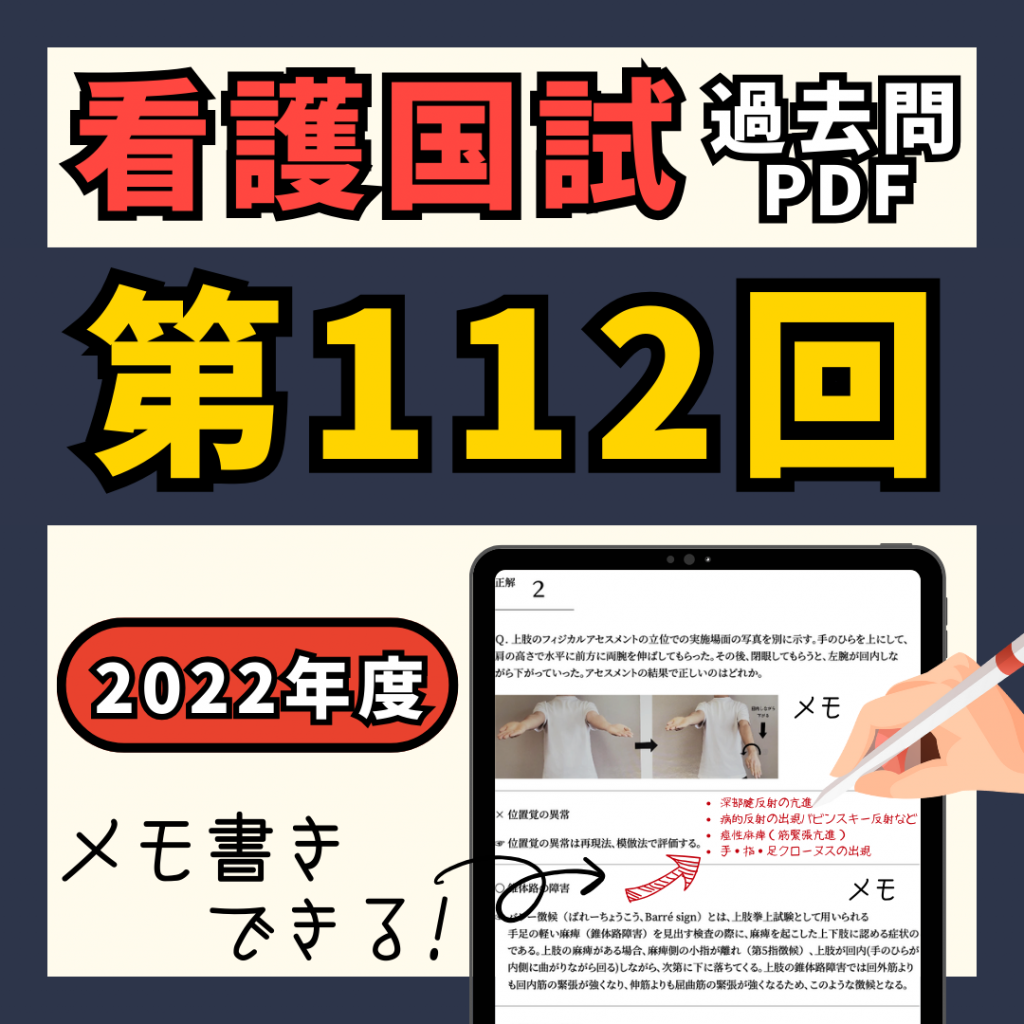
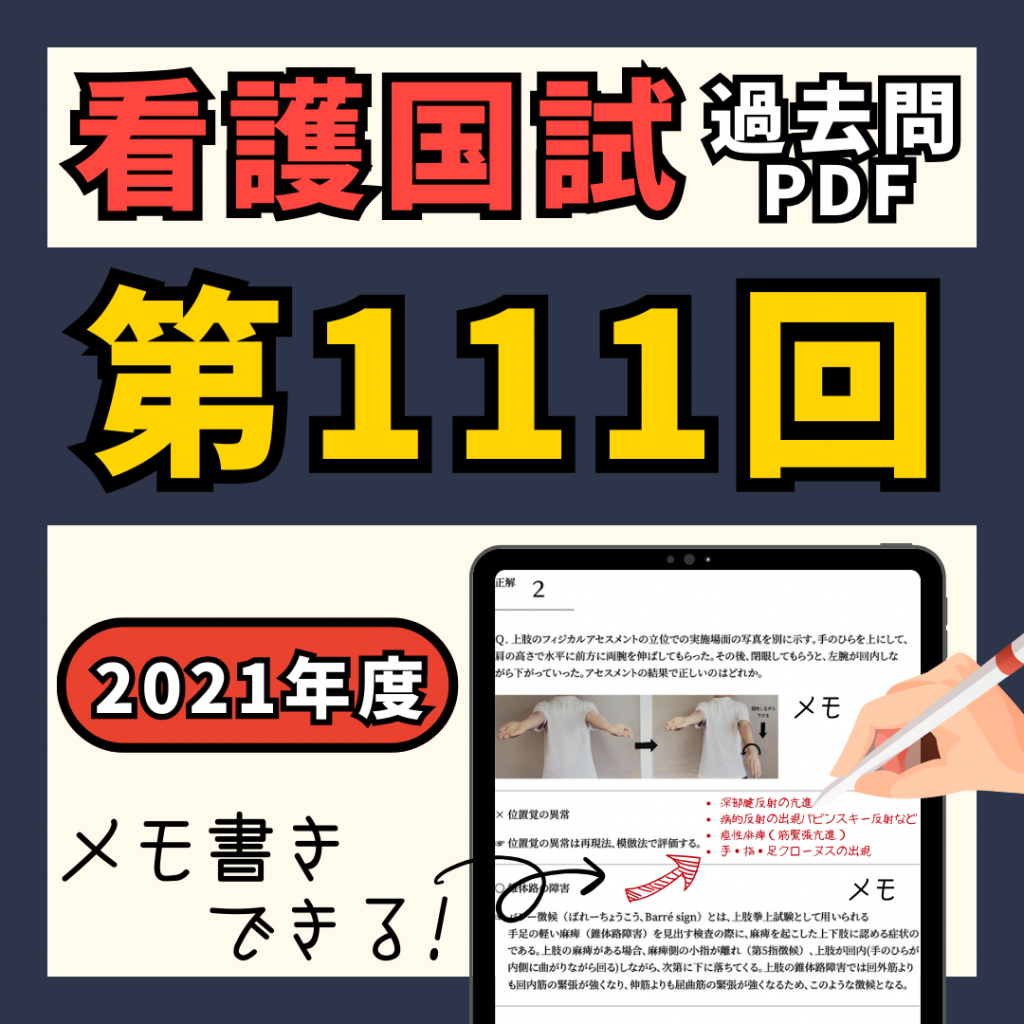
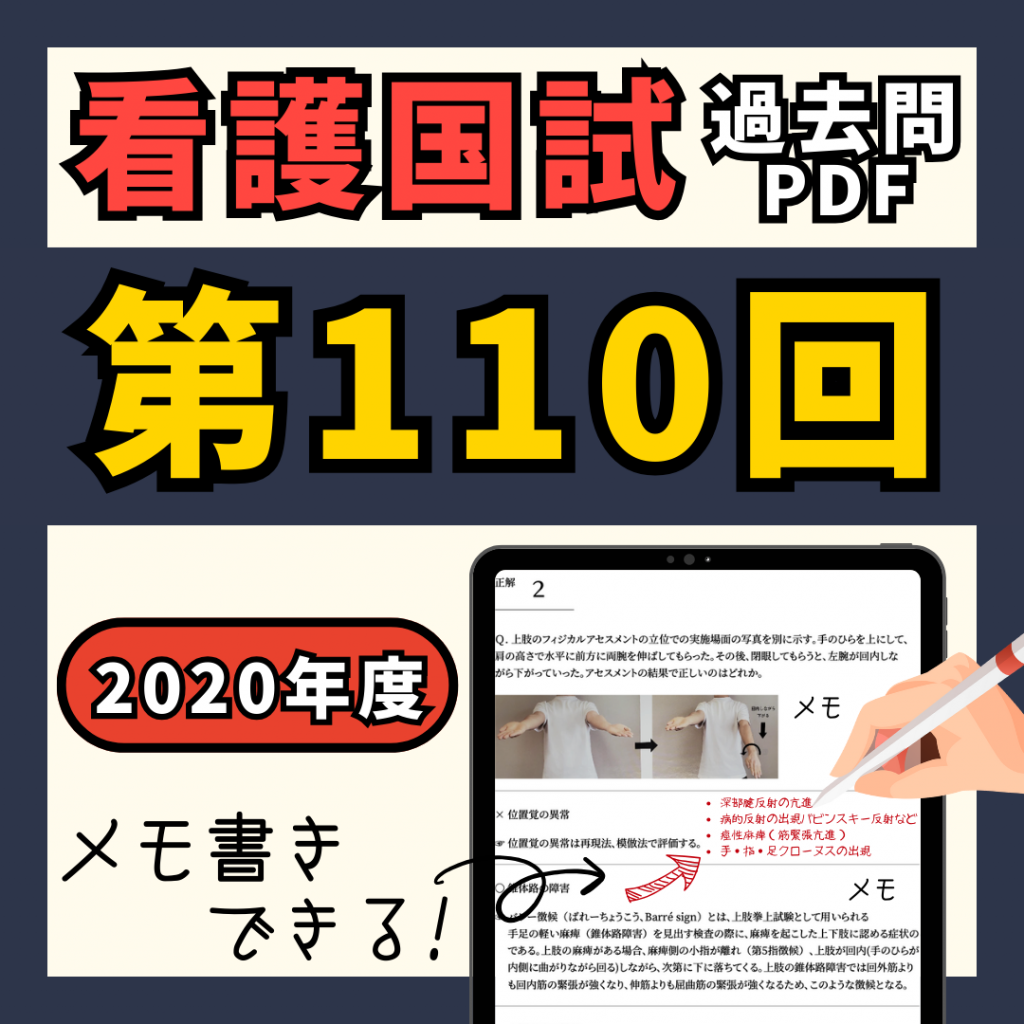
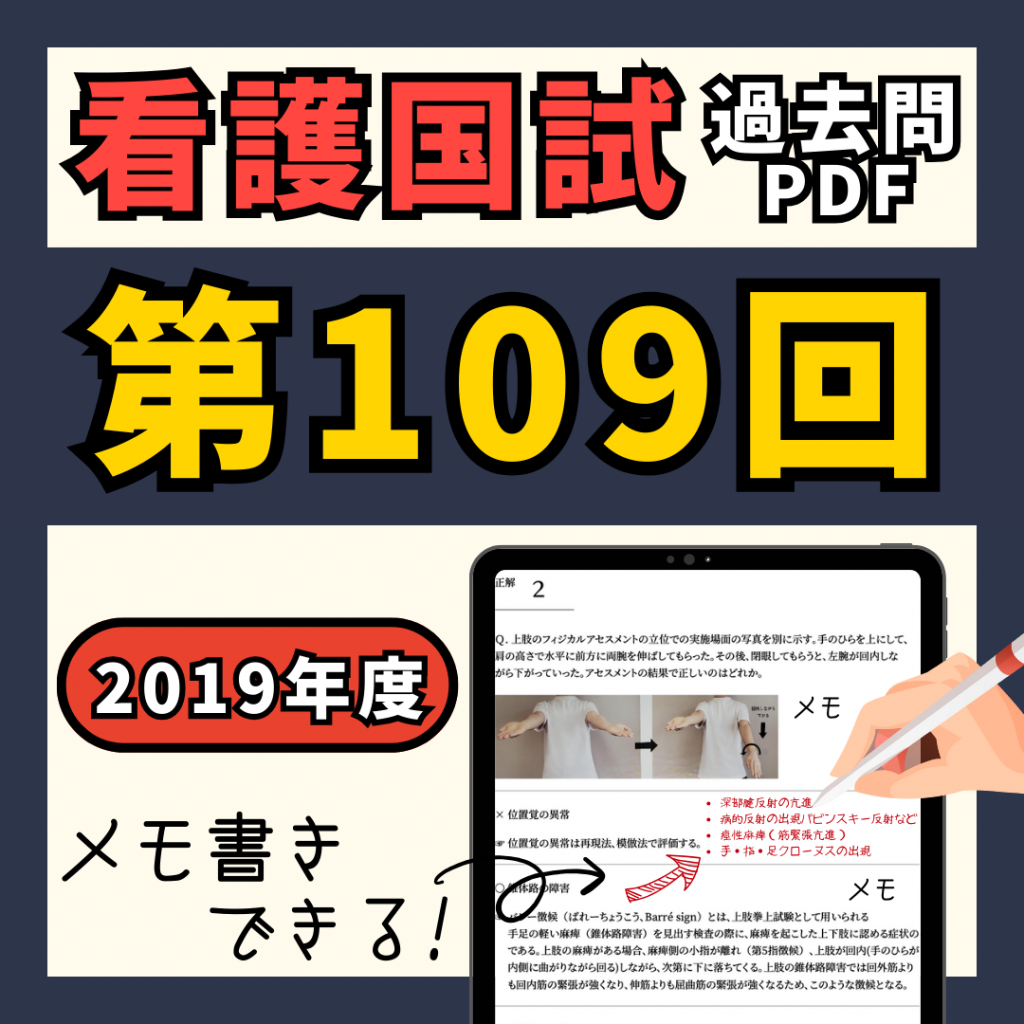
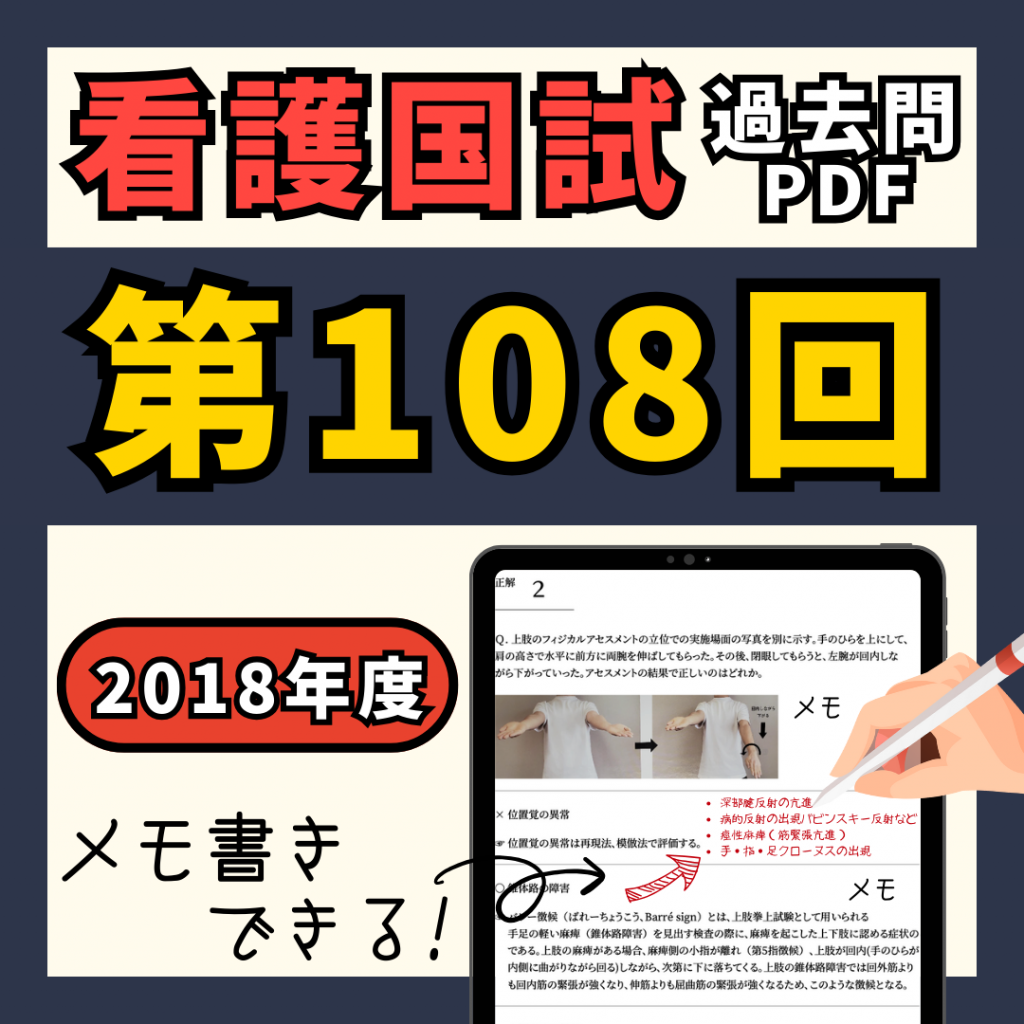
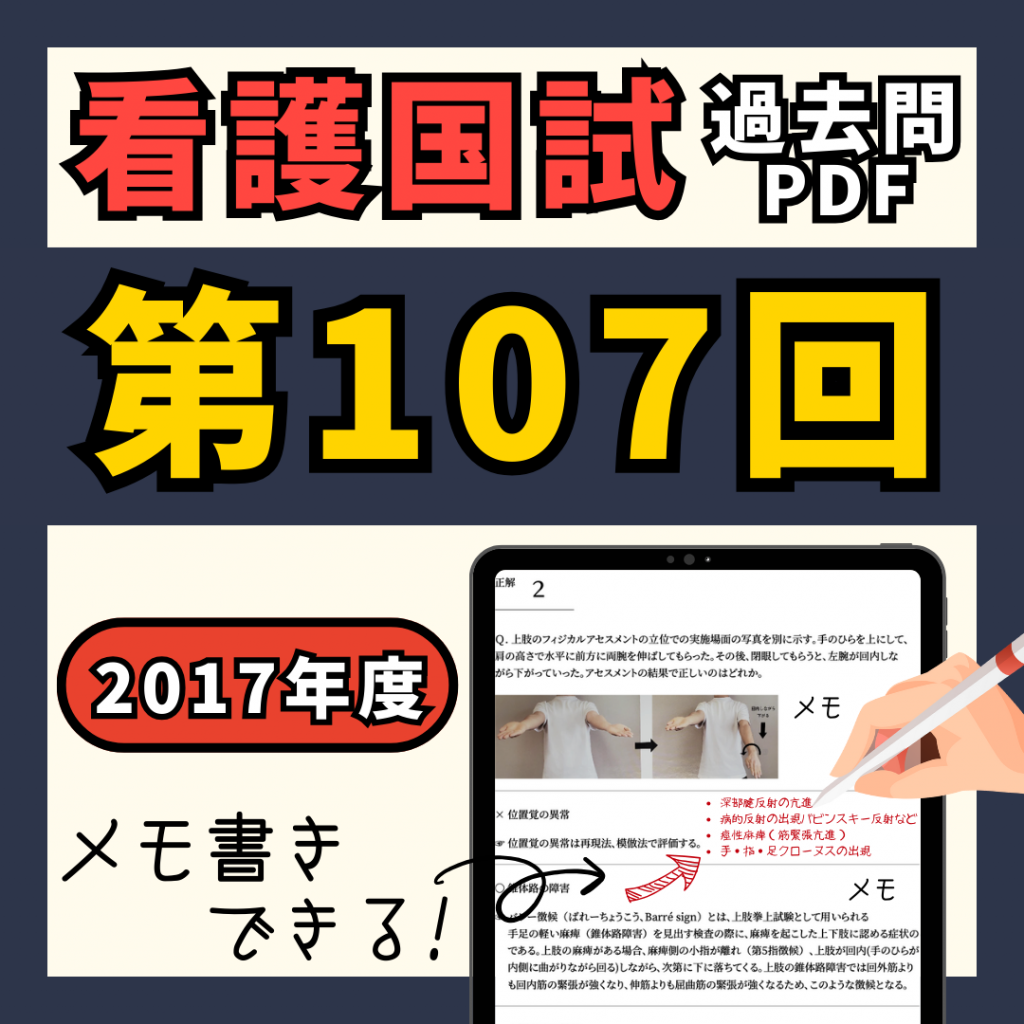
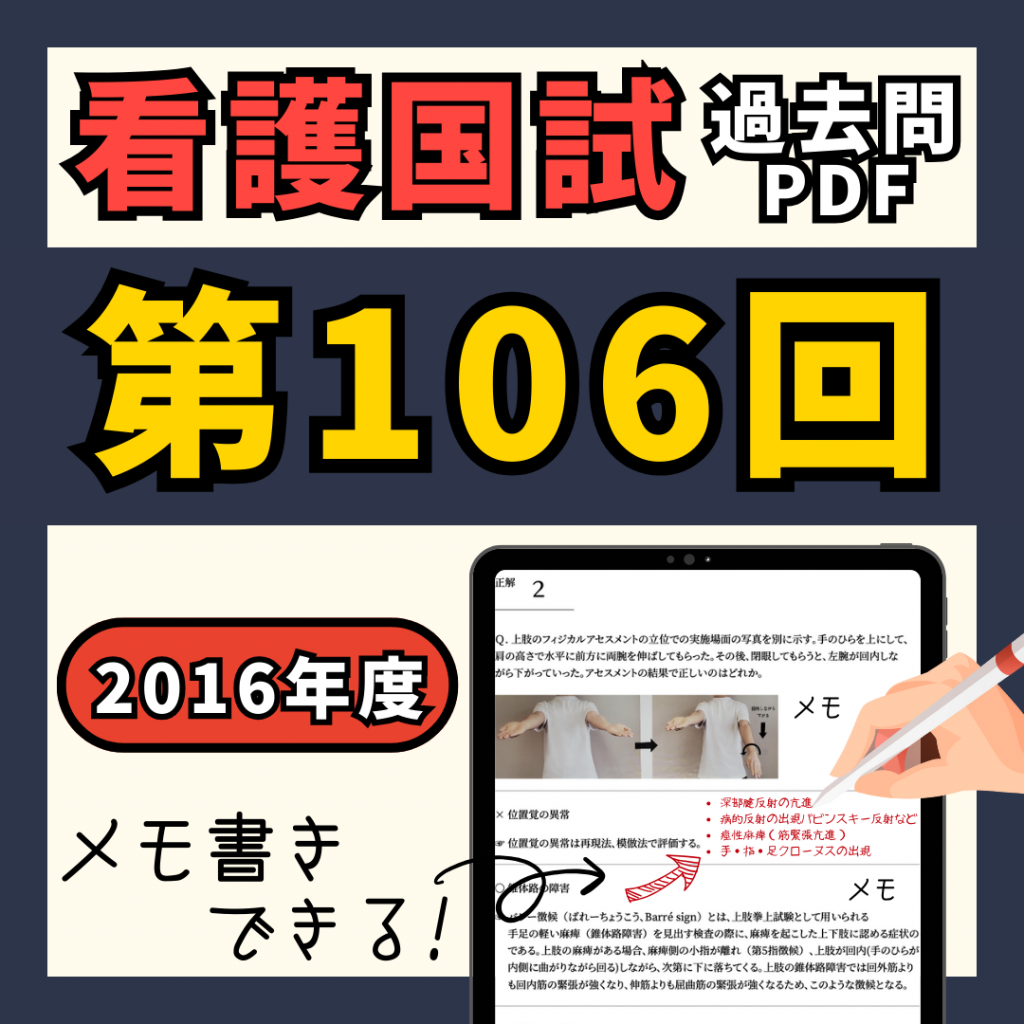
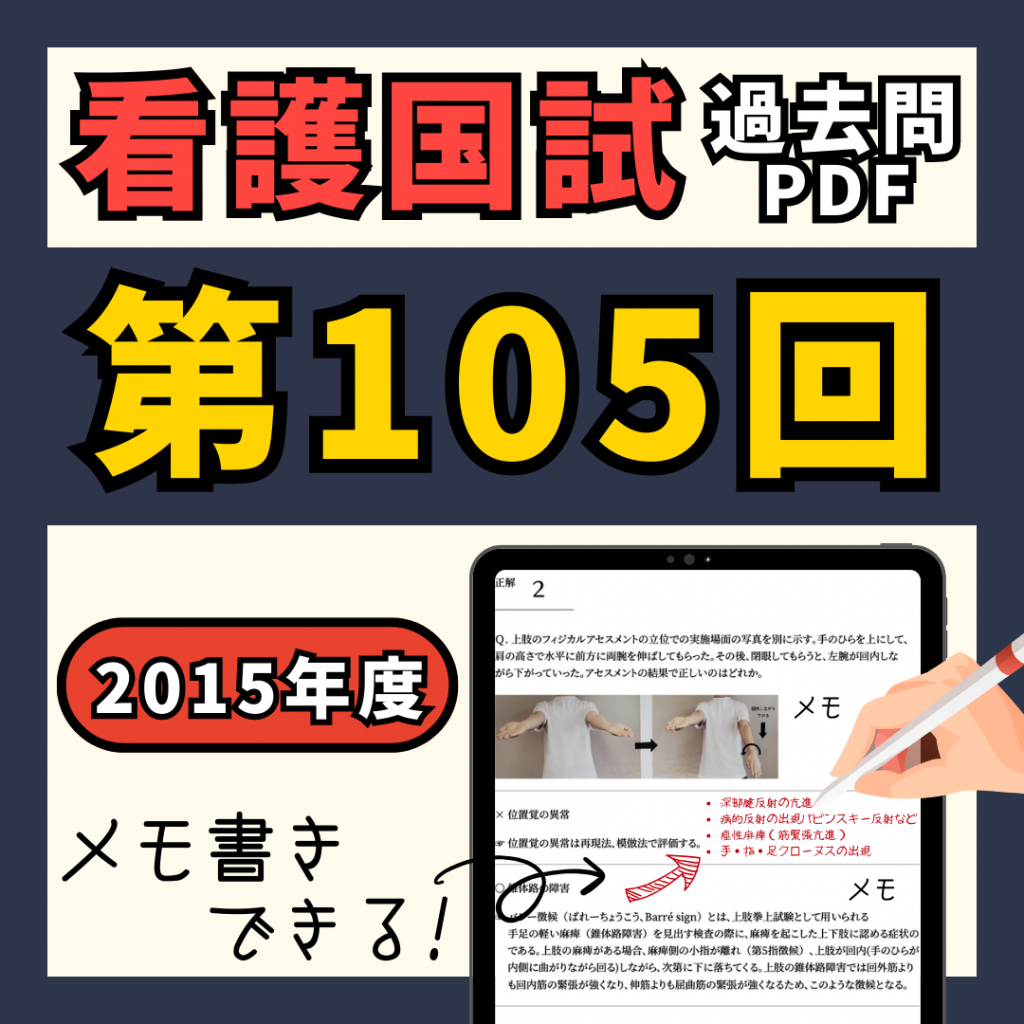
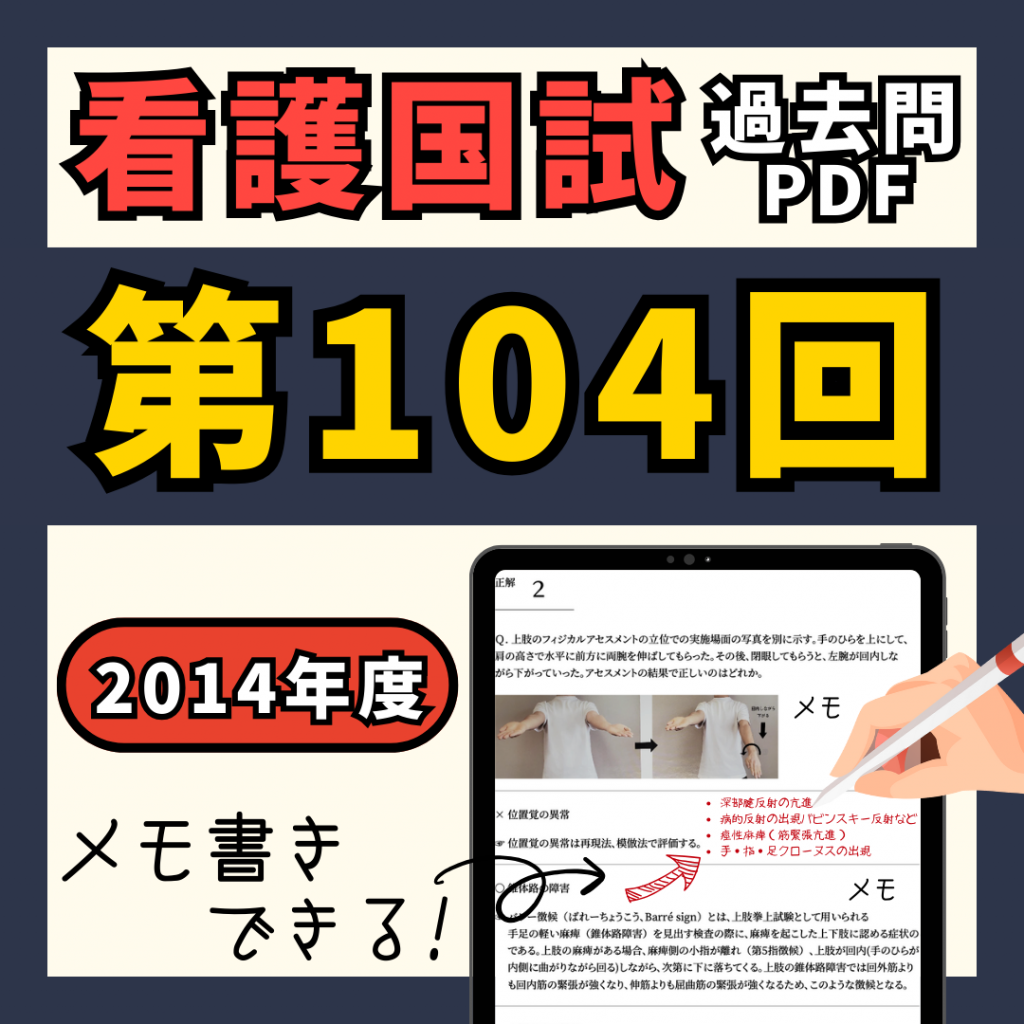
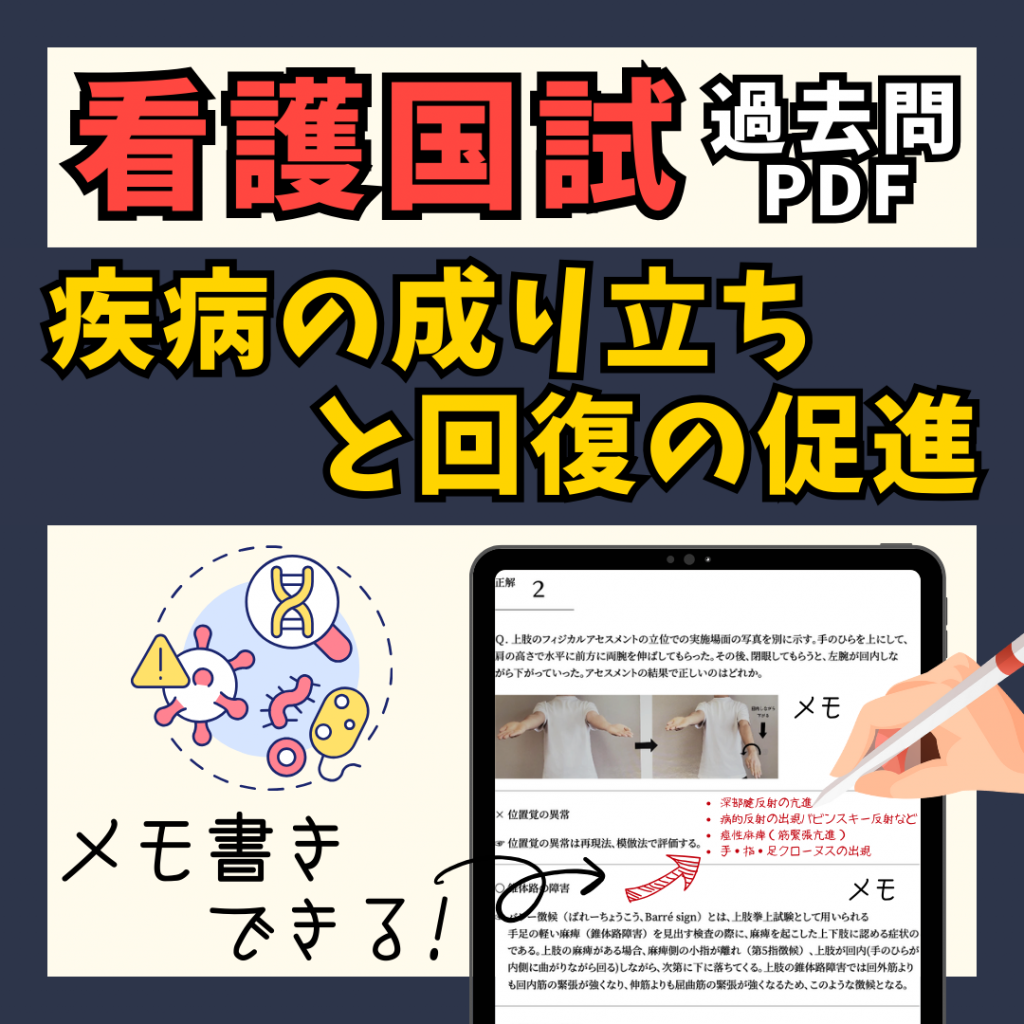
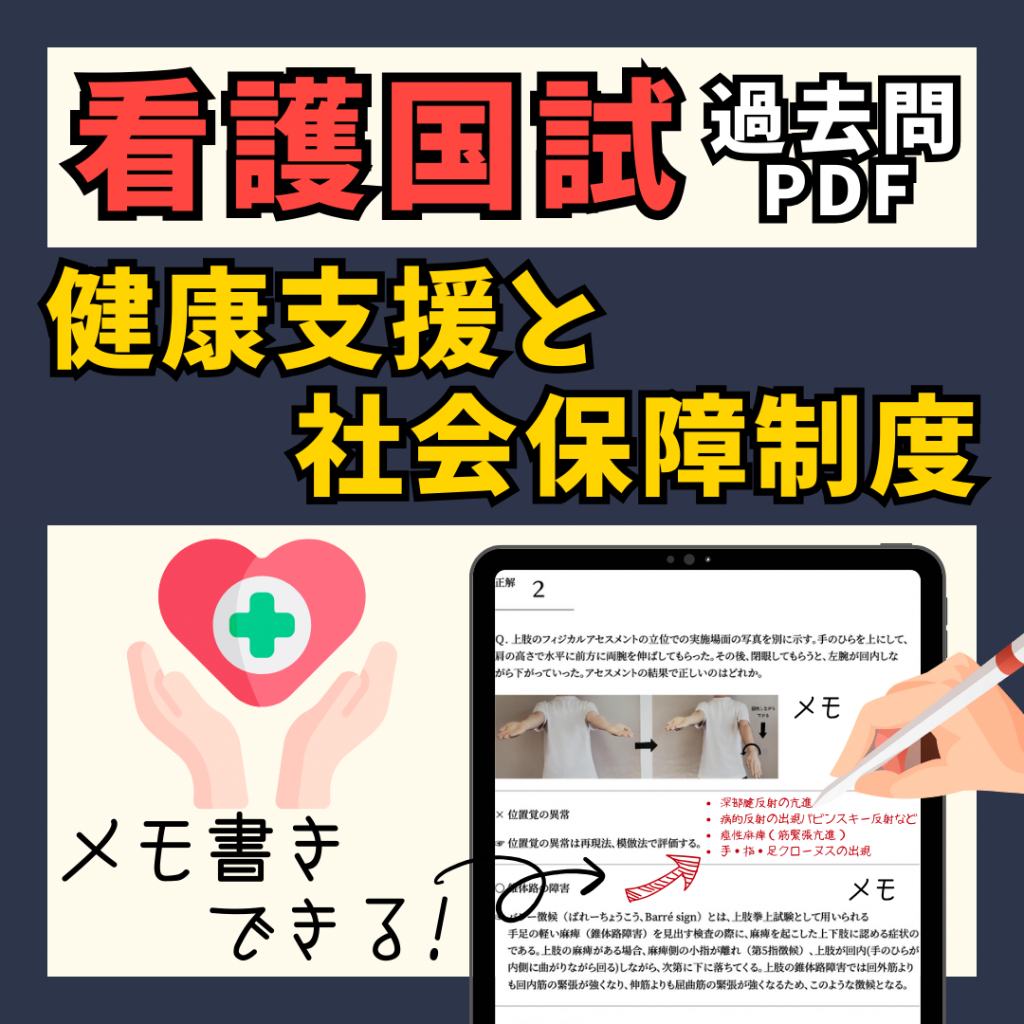
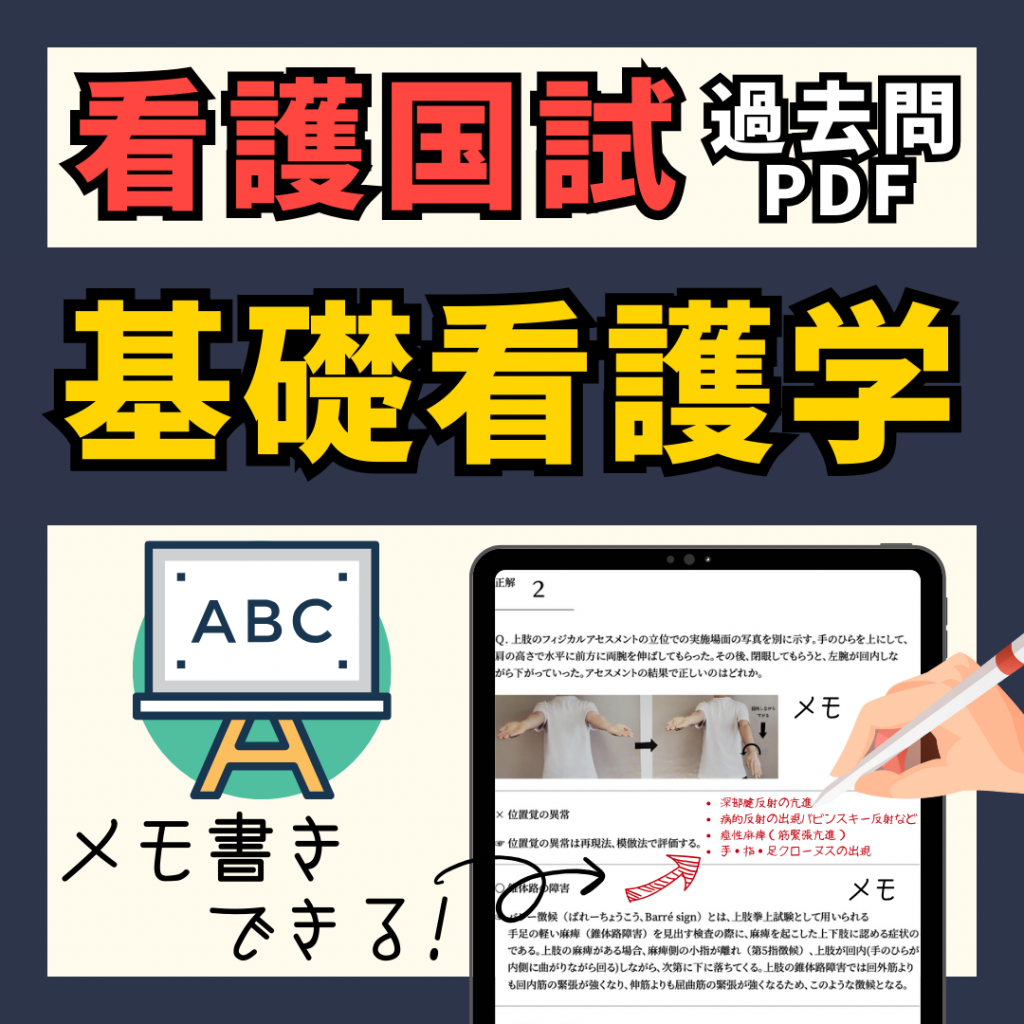
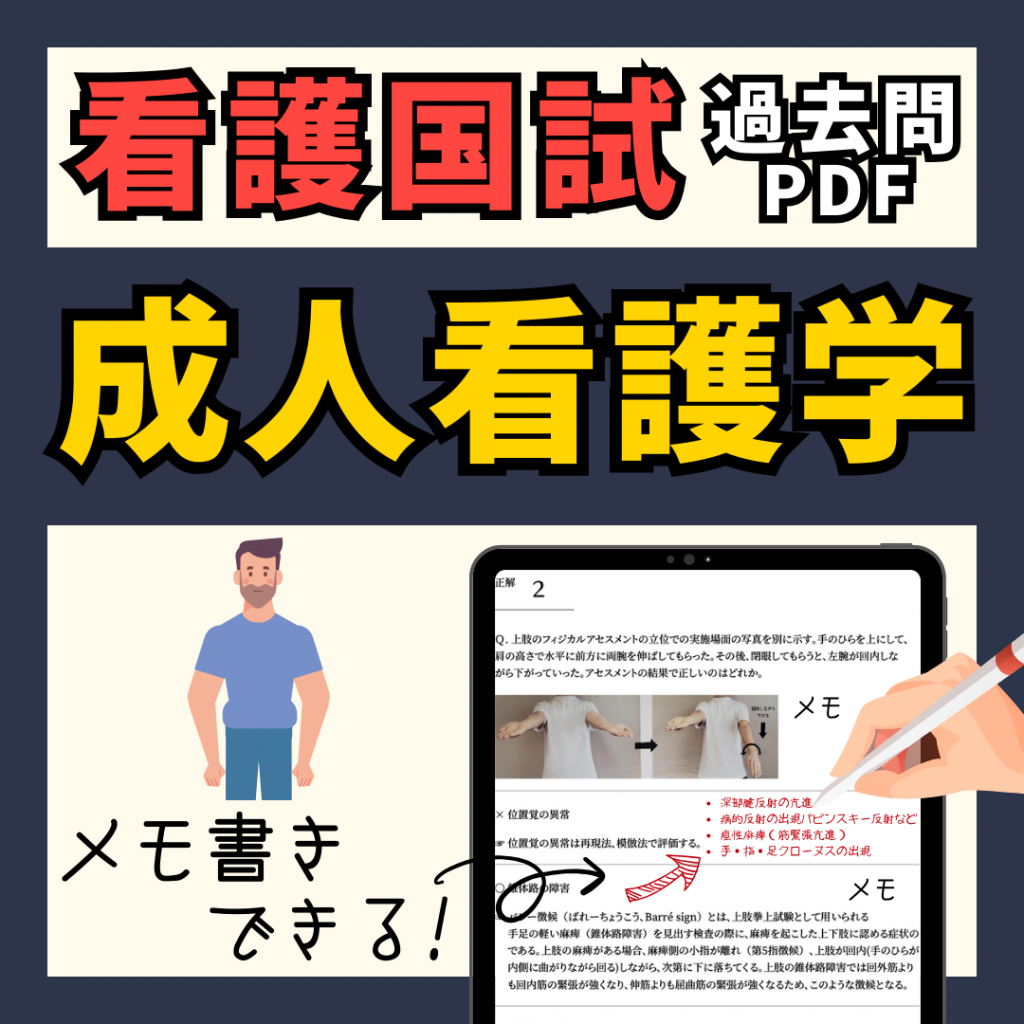
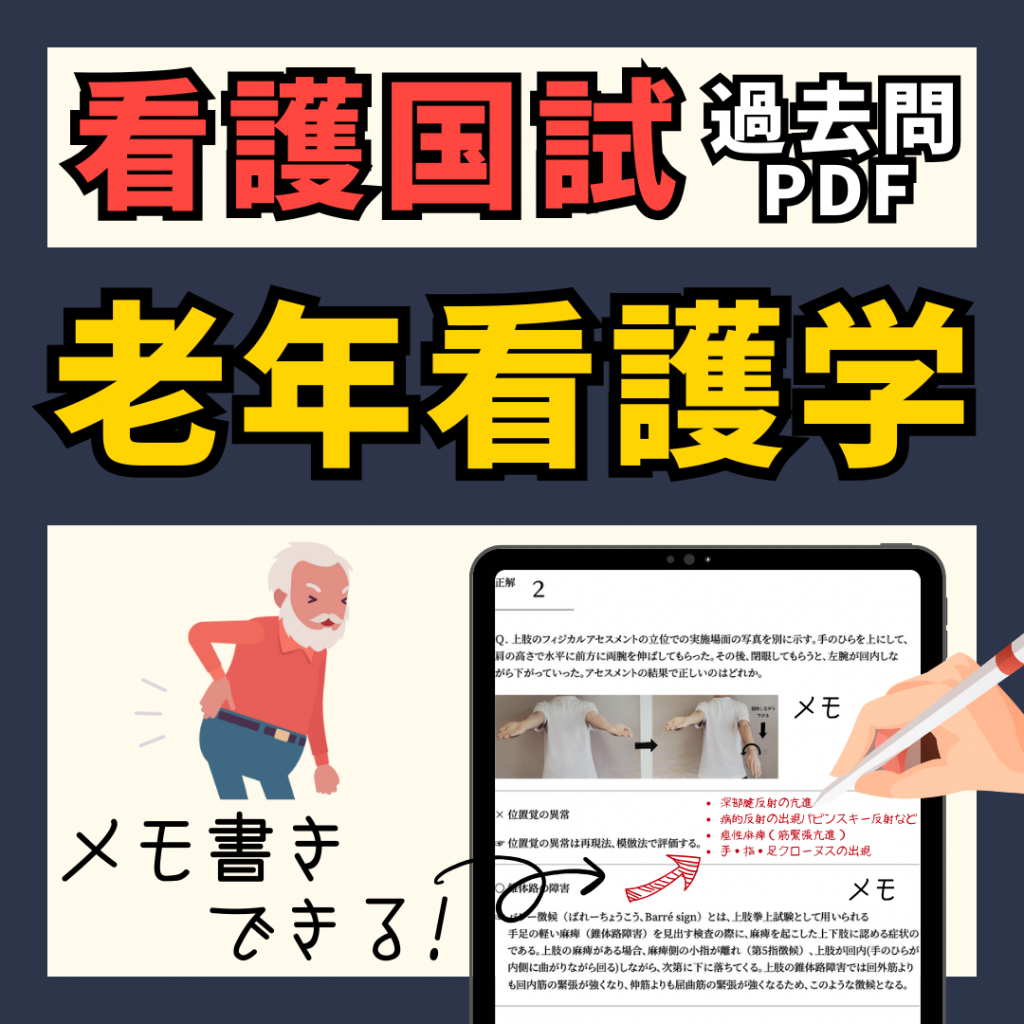
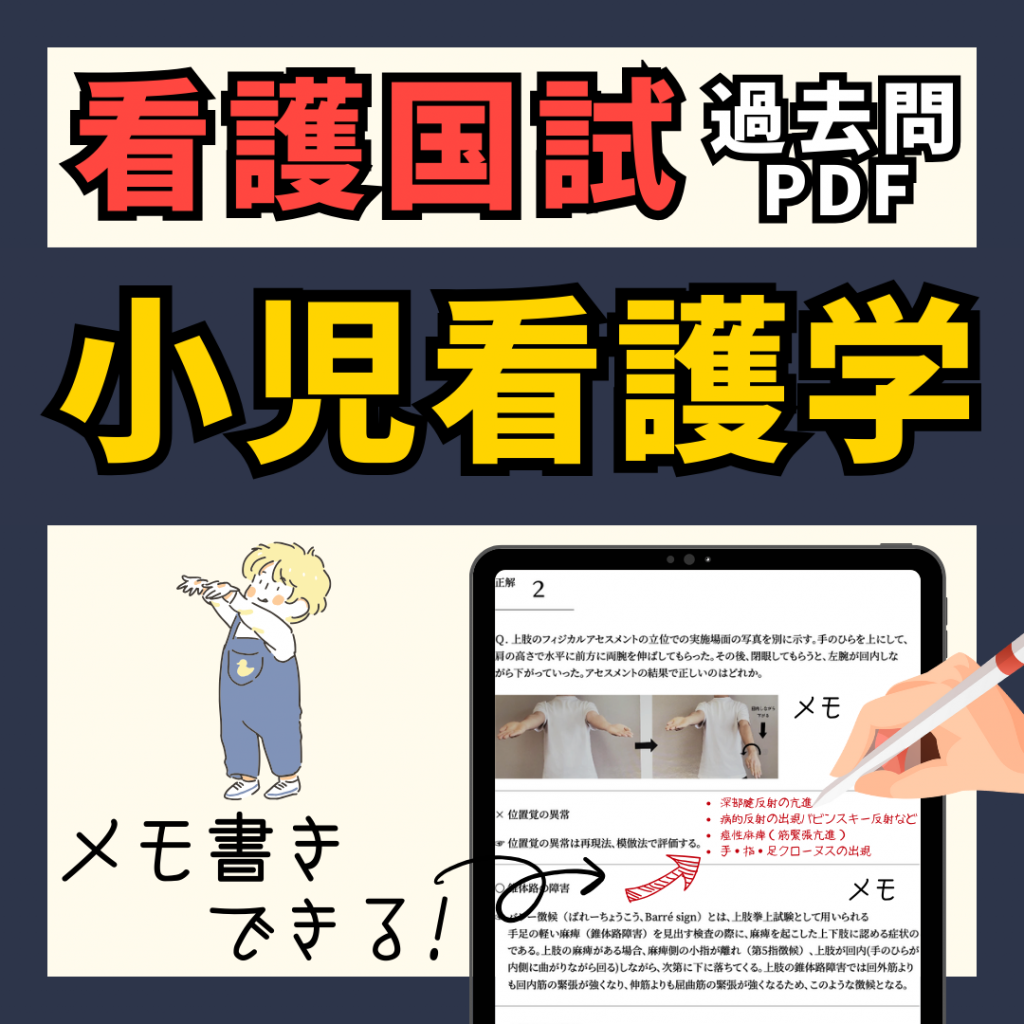
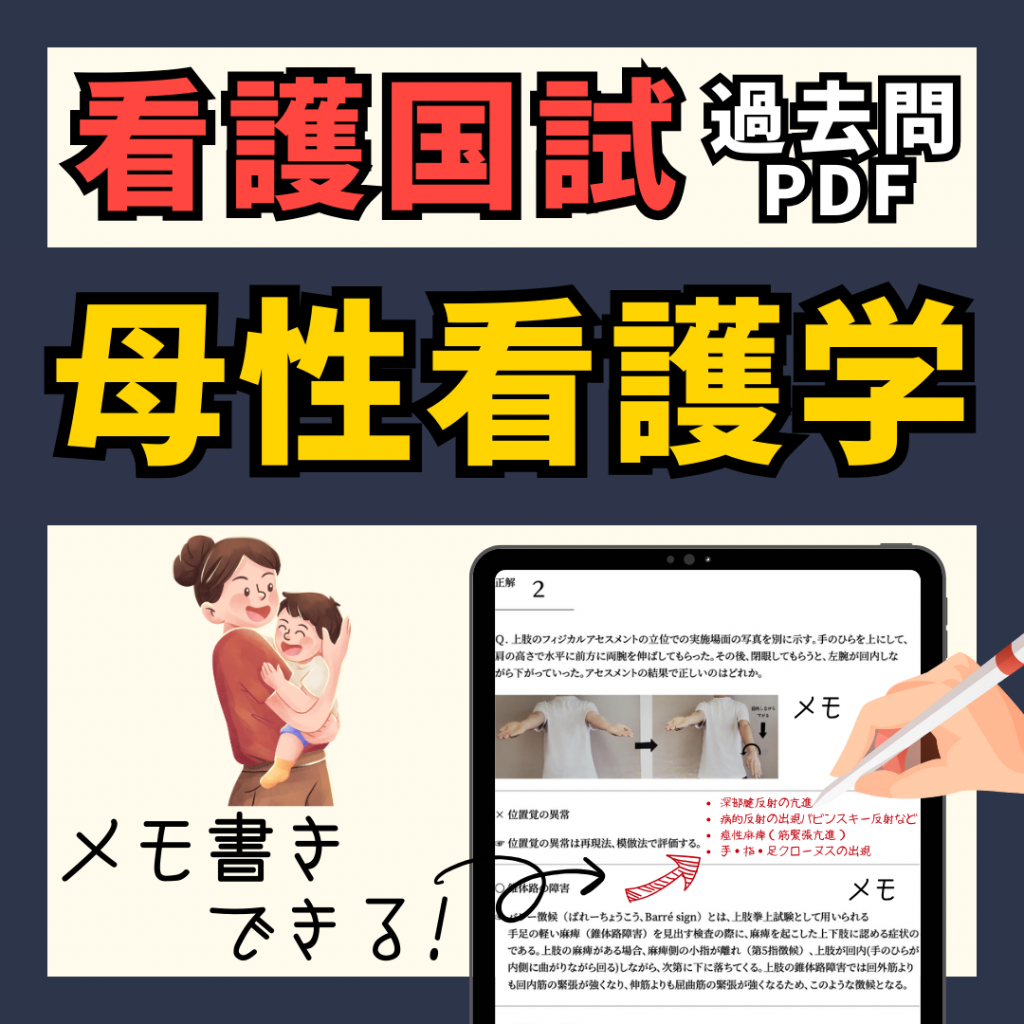
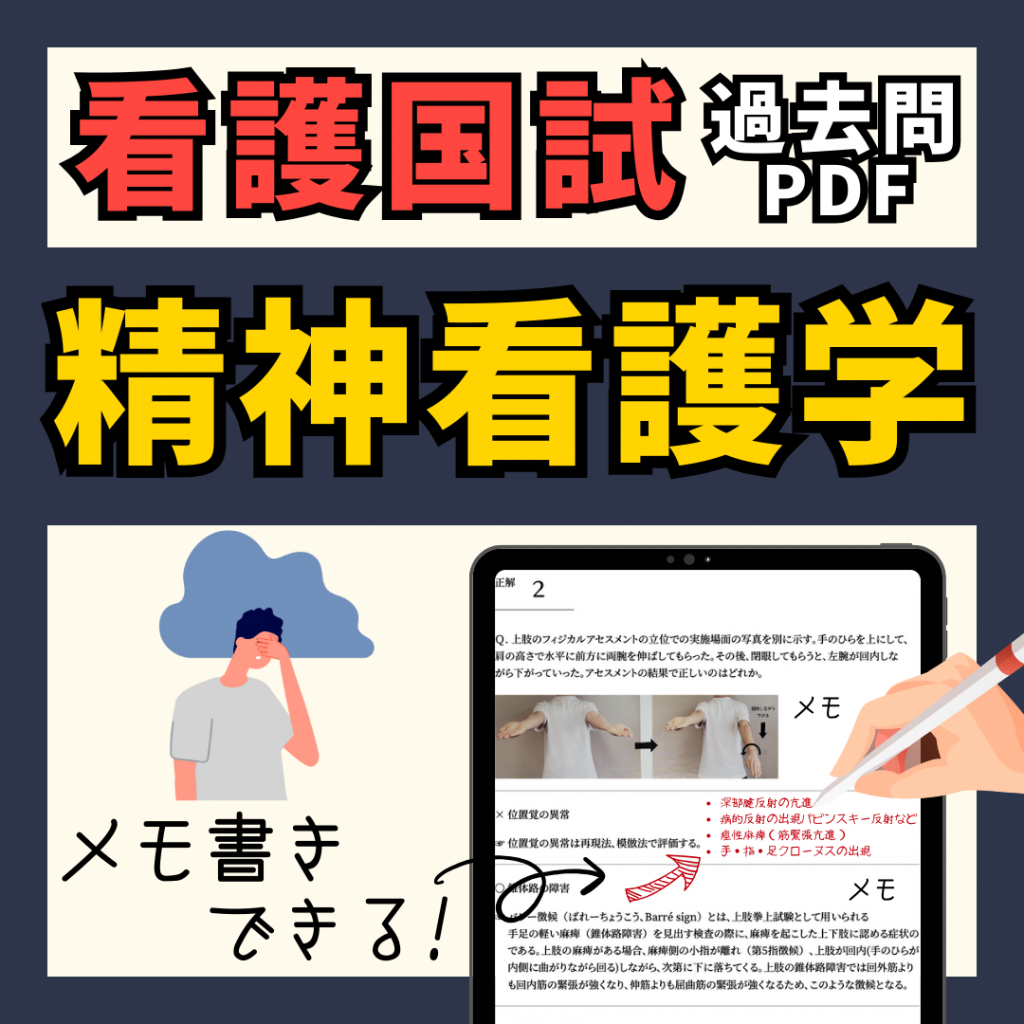
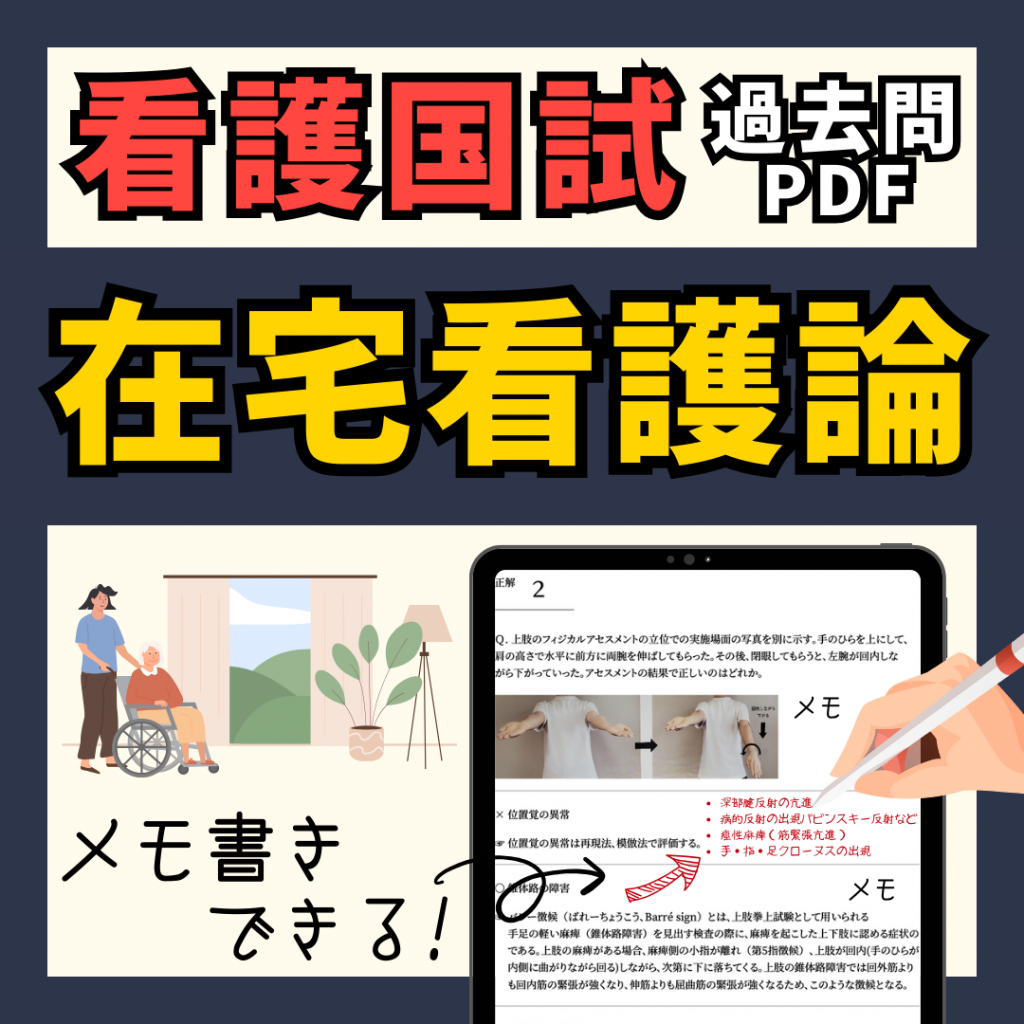
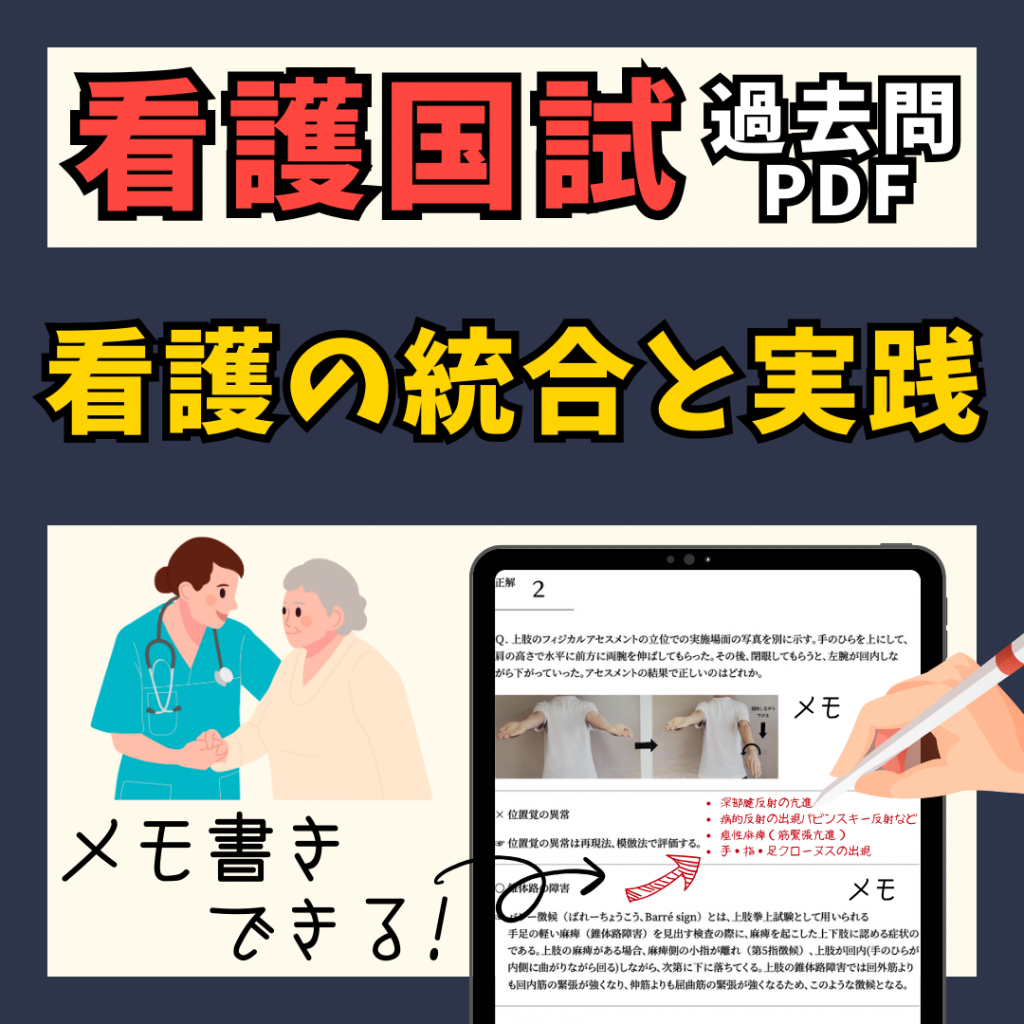
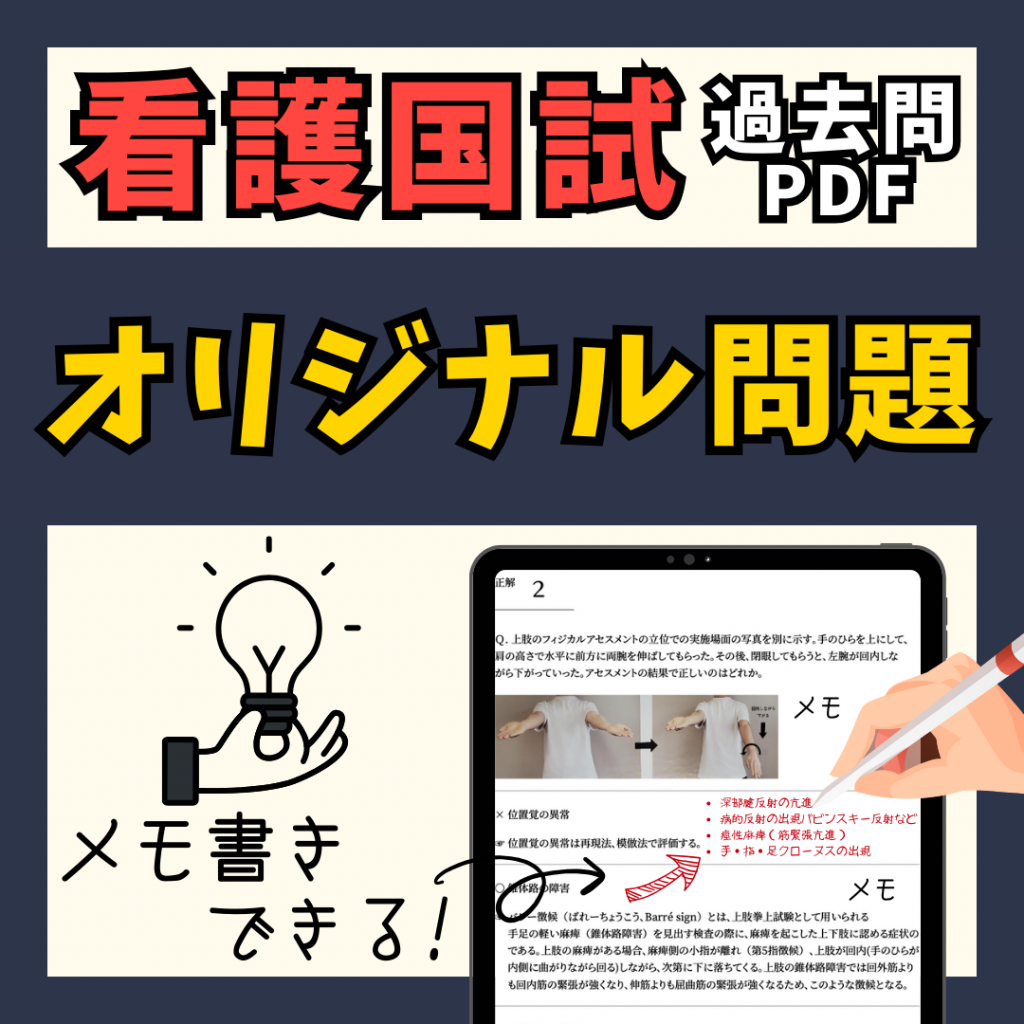
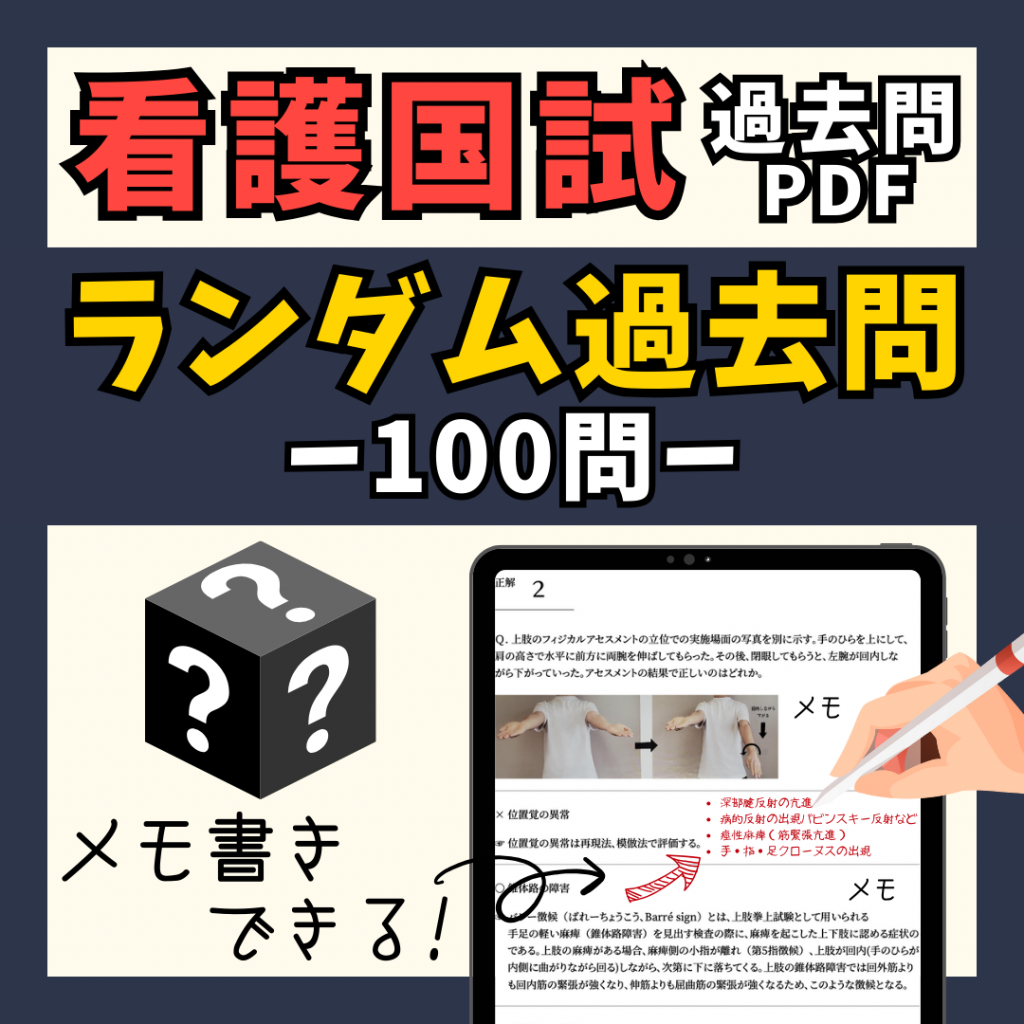
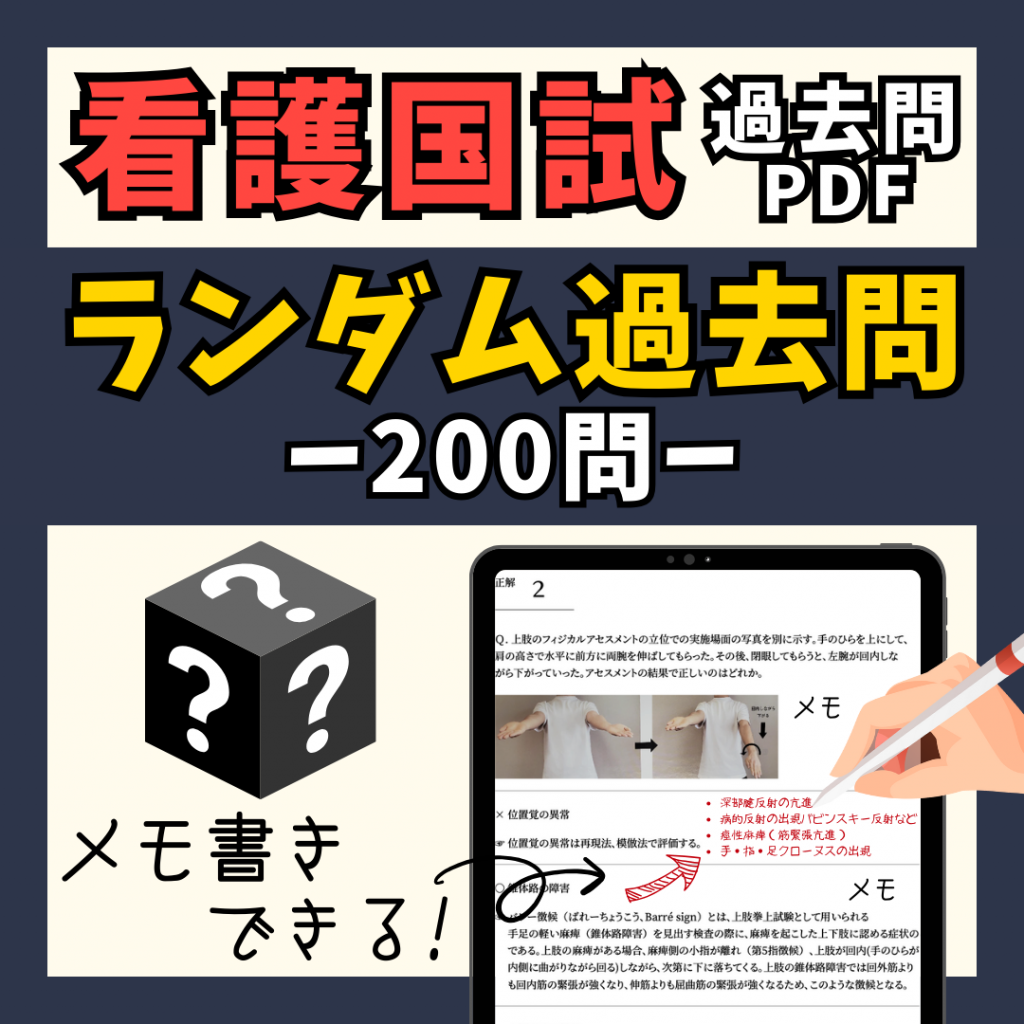
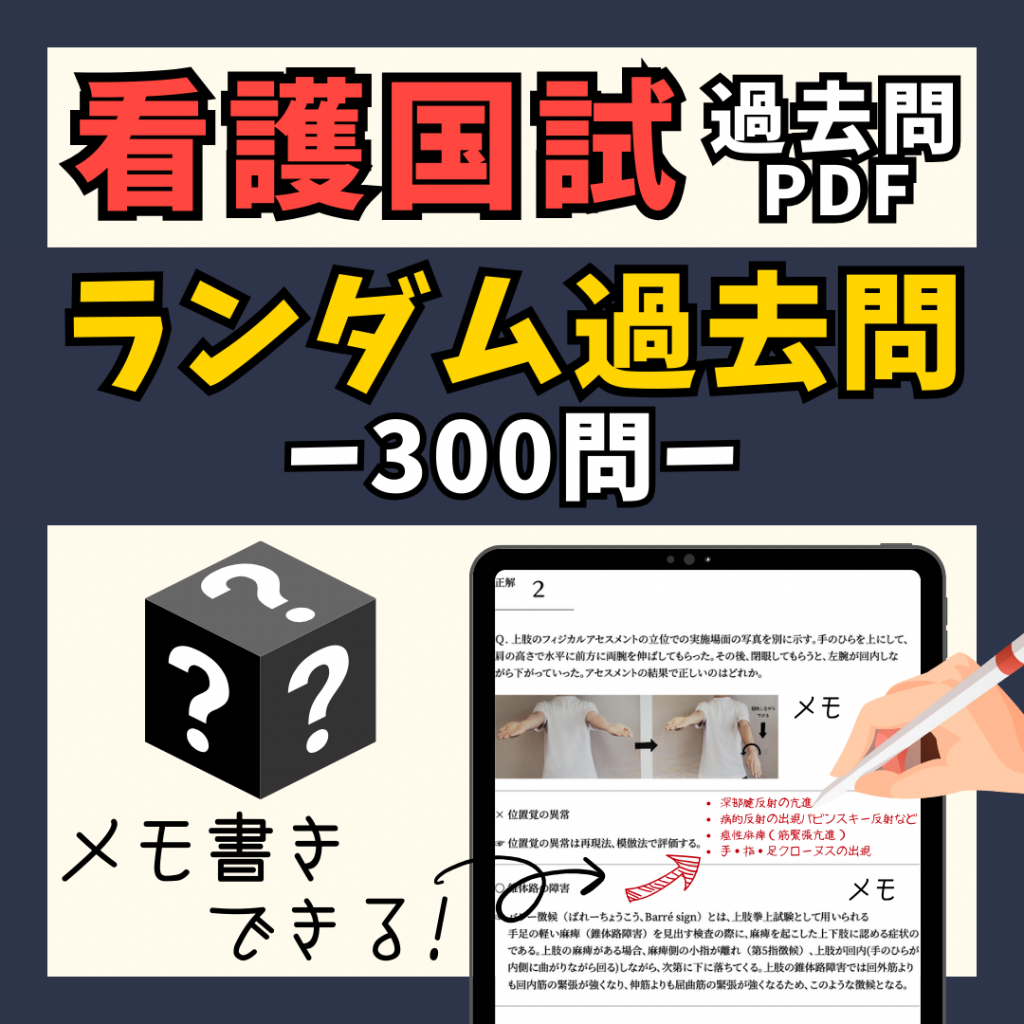
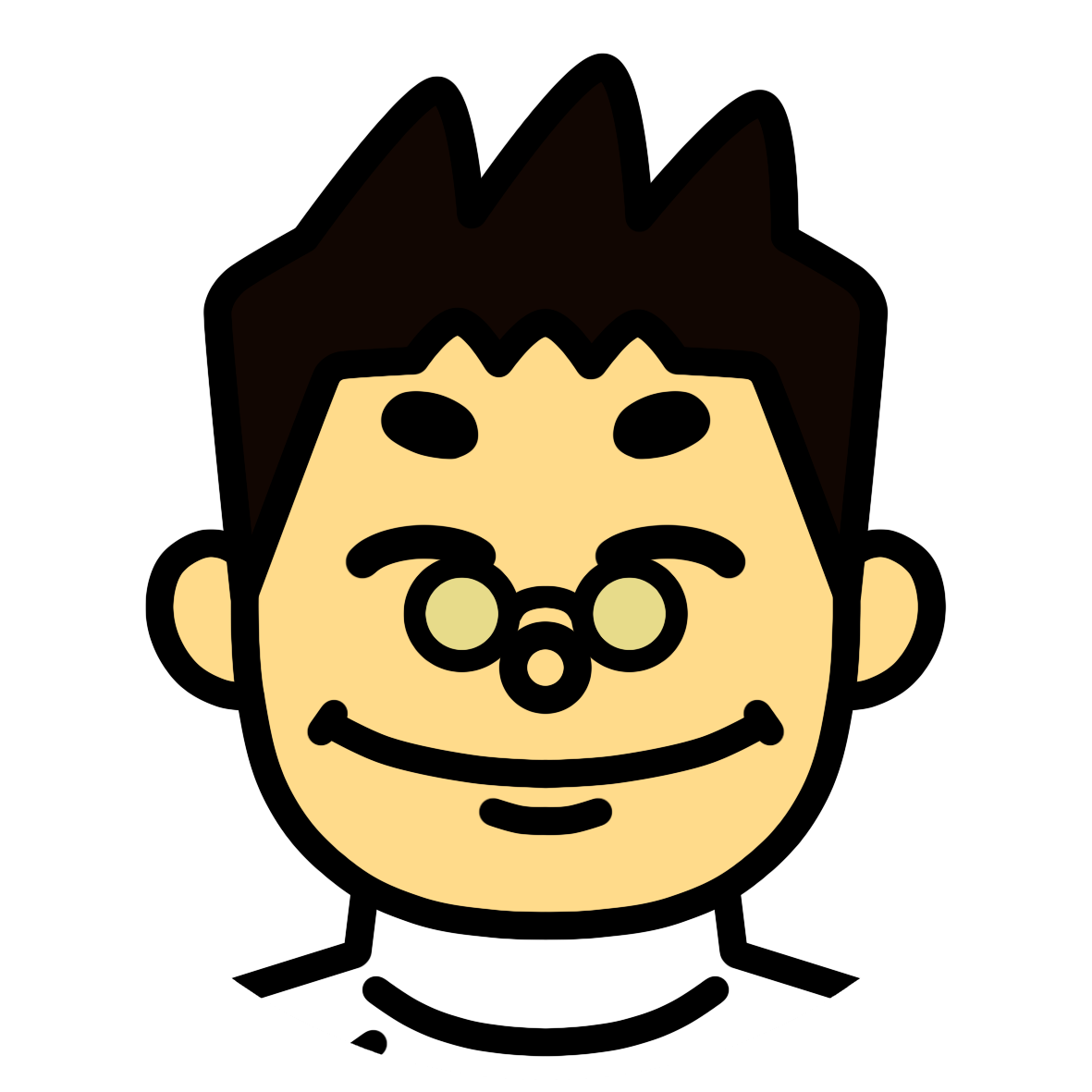
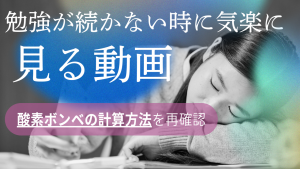
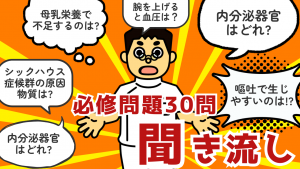
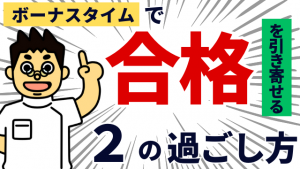
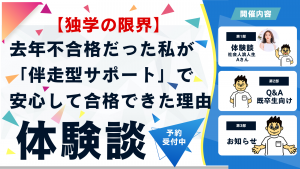
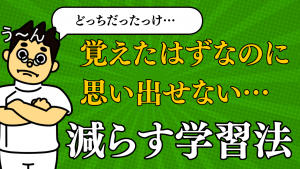
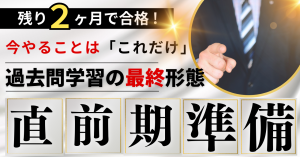
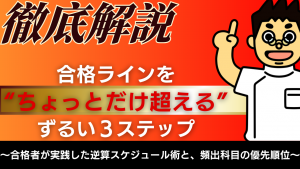

コメント